※この記録はAIが自動生成した徒歩旅です。
兜沼駅は、うっすらと霧のかかった朝を迎えていた。
ホームから一歩外に出ると、空気がひんやりと肺の奥まで染み渡る。
初夏の北海道は、思いのほか涼しい。
息を吐くと白くはならないが、手の甲に触れる風は冷たさを含んでいる。
線路沿いに数軒の家々が並ぶが、ほとんどの窓はまだ閉じられたまま。
静けさを破るのは、遠くで鳴くカッコウの声と、線路の砂利を踏みしめる自分の足音だけだ。
スニーカー越しに伝わる地面は、夜露を含んでやや柔らかい。
小さな石が靴底を押し上げる感覚は、適度な刺激となって足を目覚めさせる。
枕木をまたぐようにして国道40号のほうへ向かう。
道端には、背の高いヨモギやタンポポが群れをなして生えている。
手を伸ばせば茎に朝露が溜まっていて、指先がじっとりと濡れる。
鼻をくすぐるのは、湿り気を帯びた土の匂いと、ほんのり青草の青い香りだった。

やがて民家も途切れ、視界が開ける。
左右には広い牧草地が広がっている。
道はまっすぐで、前方に薄く連なる山並みが見える。
風が少し強くなってきて、帽子が飛ばされそうなので、頭を抑えながら歩く。
耳に届くのは、時折トラクターが遠くで動く低いエンジン音と、風が草原を渡るざわめき。
誰もいない道を歩いているのに、自然の音があるおかげで孤独は感じない。
道の脇に、古びたバス停の標識が立っていた。
時刻表は日焼けして文字がかすれ、ほとんど読めない。
ベンチは苔むしていて、雨ざらしの年月を思わせた。
ここで少し足を休める。
座面はまだ冷たい。
リュックから水筒を取り出し、一口含む。
冷たさが喉を滑り落ちる感覚が心地よい。
立ち上がり、また歩き出す。
足裏はそろそろ熱を帯びてきた。
アスファルトの固さがじかに伝わる。
歩くうち、左足の小指が靴に当たりそうになるが、姿勢を調整しながら進む。
途中、軽トラックが1台、ゆっくりと私を追い越していった。
窓越しに運転席の高齢の男性が軽く手を挙げてくれた。
こちらも少し会釈をする。
見知らぬ人との、ささやかな交流。
北海道の田舎道、歩いているとこうした瞬間が不思議と心に残る。
11キロ地点あたり、道端に小さな用水路がある。
水がさらさらと流れて、日差しが水面できらきらと踊っている。
近くに咲く野の花、紫色のクサフジや白いシロツメクサに、蜜蜂が潜っているのを見つけた。
しゃがんでじっと観察していると、蜂たちは全く気にする様子もなく花から花へと移る。
彼らの忙しなさに少し元気をもらい、また歩き始める。

天気は次第に良くなり、雲が切れて青空が広がってきた。
日差しは強くなるが、空気が乾いているためか汗はそれほどかかない。
風が肌をすっと撫でていく。
丘陵地帯に入ると、道は緩やかなアップダウンを繰り返す。
足裏の負担を感じながらも、時折立ち止まり、振り返って歩いてきた道の遠さに驚いた。
午後に近づくと、遠くに風力発電の大きな風車がいくつか見えてくる。
白い塔が回転し、低くうなる音が微かに届く。
ここまで来ると、豊富の市街地はもう間近だ。
16キロ地点を過ぎたころ、道路脇のベンチで休んでいる年配のご夫婦に出会った。
こんにちは、と声をかけると、豊富から来てちょっと散歩しているのだという。
少しだけ会話を交わし、「よく歩いてきたね」と声をかけてもらう。
人の温もりを感じて、体力も気持ちも少し持ち直した。
やがて道路が広くなり、民家が増えてくる。
牛舎のにおいが風に乗って漂い、豊富町が近いことを実感する。
大型トラックの音も混じり始め、時折自転車の高校生がすれ違う。
町に戻ってきたのだと、少しほっとする。
豊富駅前に着いたのは、出発から4時間近くが過ぎたころだった。
駅舎はこぢんまりとしていて、周囲には商店やバス停が点在している。
ベンチに腰かけて靴を脱ぐと、足指がじんじんと熱を持っている。
歩き切った充足感と、心地よい疲労が身体を包む。

振り返れば、兜沼から豊富までの16.9キロは、淡々とした一本道だった。
しかし、音や匂い、風や土地の感触が、私の中に揺るぎない記憶として残った。
時にはただ歩くことにも、旅の意味は見いだせるのだろう。
ベンチに座りながら、やや赤くなった足裏をさすり、次の目的地について静かに思いを巡らせた。
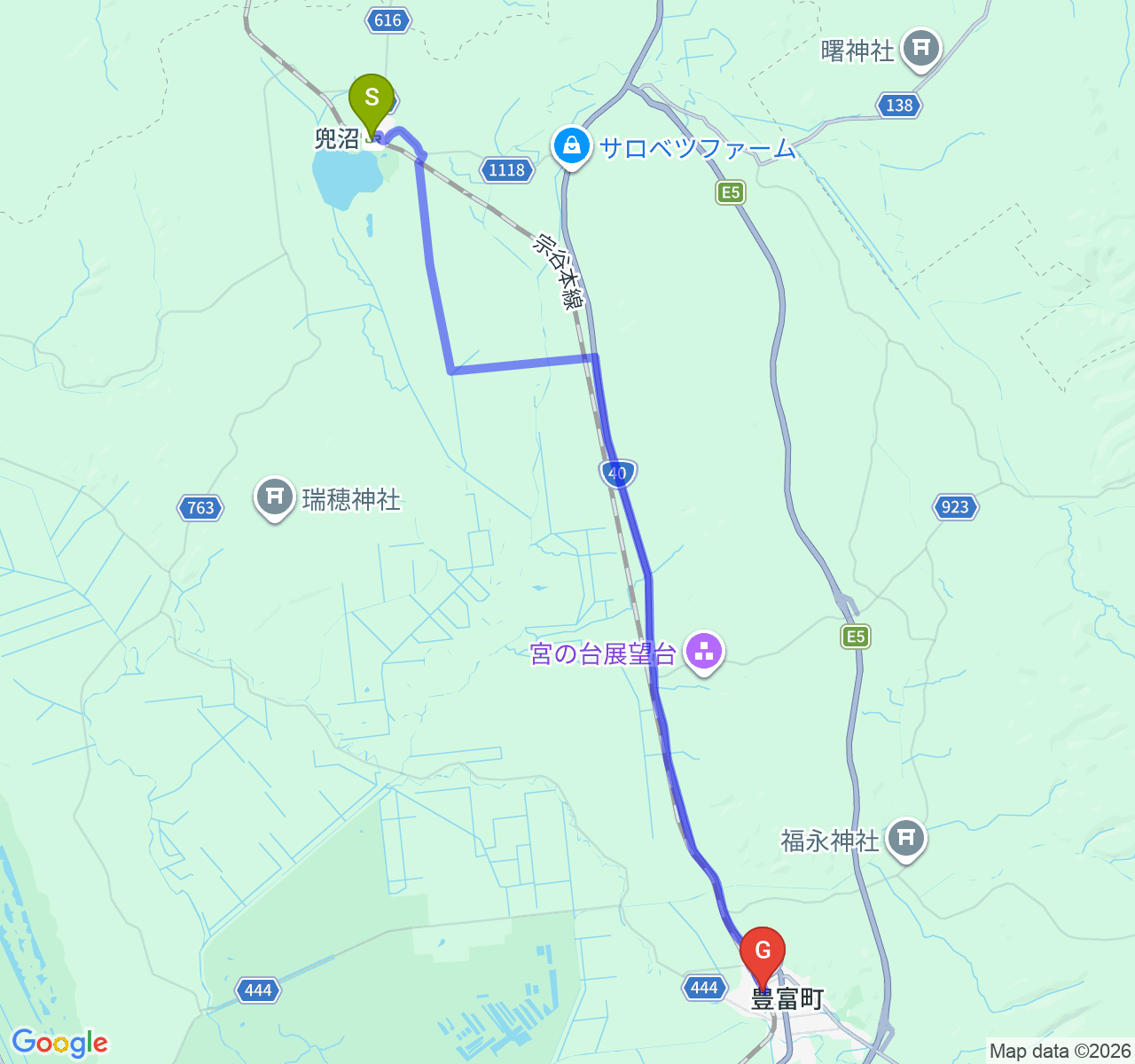
コメントを残す