※この記録はAIが自動生成した徒歩旅です。
宗谷線・勇知駅。
六月の午前八時過ぎ、ホームに立つと、ひんやりとした空気が頬を撫でた。
汽車を降りたのは私ひとりだけ。
線路の向こうはまだ薄曇りで、海からの湿った風が時折草むらを揺らしている。
駅舎の小さな窓に、遠く利尻の山影が映っていた。
宗谷の朝は静かだ。
スニーカーの底に伝わるコンクリートの冷たさに一瞬身震いし、しばらくホームに立ち尽くす。
辺りには甘い草の匂いが混ざる。
駅前の道標を眺め、歩き出した。
アスファルト道を北へ。
兜沼まで、約六キロ弱の道のり。
北海道の郊外は道がほぼ真っ直ぐで、左右には防風林と畑が広がっている。
歩き始めて十分ほど、足音だけが響く。
軽い朝露で路面が少し湿っているのか、靴裏が時折キュッと鳴る。
空気は冷たいが、動き始めるとじわじわと体が温まり、額にうっすら汗が滲む。
道沿いのポプラは新緑で、その葉が風に揺れて朝の日差しをちらちらと反射する。

途中、農家の軽トラックがゆっくり近づいてきて、私の横を通る時、窓越しに運転席の年配男性が軽く会釈してくれた。
北海道らしい、無駄のない気遣い。
トラックが遠ざかると、また静けさが戻る。
遠くでカッコウが二度鳴いた。
時折、畑から土の匂いが強くなる。
育ち始めたジャガイモの葉が青々としている。
三十分ほど歩いたところで、左手に小さな用水路が現れる。
水は澄んでいて、底の砂利が朝日に光る。
そばの草むらではキジが一羽、じっと何かを見つめている。
私が足を止めると、キジは警戒して遠ざかった。
用水路の水音が小さく耳をくすぐる。
少し腰を下ろしてペットボトルの水を飲む。
周囲は野鳥の声と、遠くの牛舎から漏れる牛の鳴き声だけ。
そういえば、道沿いには時折ガマの穂が並び、湿地の気配を感じる。
再び歩き始める。
靴底が砂利混じりの路肩を踏むたび、ごつごつとした感触が伝わってくる。
温度は昼に向けて少し上がり、薄曇りの空が明るさを増す。
北風はまだ冷たく、手をポケットに入れて歩いた。
左右に広がる畑には、広大な空が被さる。
宗谷の大地は、歩いていると時間の感覚が曖昧になる。
目の前の道がずっと続いているような錯覚に陥る。
道端に、色褪せた小さな祠が立っているのを見つけた。
屋根の下には古い紙垂。
足を止めて眺めると、誰かが新しい花を供えていた。
地元の人に守られてきた場所なのだろう。
祠の前で、ふっと風が吹き抜け、草花の香りが強まる。
ここで一息、深呼吸。
空気が肺いっぱいに広がり、少し眠気も覚えた。

そうしてまた歩く。
道はややカーブし、遠くに兜沼の森が見えてくる。
木々の色が濃くなり、沼の気配が近づく。
足元の砂利がしだいに湿地の泥に変わる。
靴底がぬかるみに沈み込み、冷たい感触が伝わる。
沼地から立ち上る湿った匂いは、北海道らしい野生の香りだ。
前方から、青いジャンパーを着た女性が犬連れで歩いてきた。
すれ違いざまに「おはようございます」と声をかけられる。
犬は白く、くるくるした尻尾を振りながら、私の靴をくんくん嗅いでいた。
「兜沼までですか」と尋ねられ、「はい」と答えると「この季節、湿地の花がきれいですよ」と教えてくれた。
たしかに、道端でアヤメらしき紫色の花が咲き始めている。
犬と女性は森のほうへ消えていった。
兜沼駅が近づくにつれ、鳥の声が増える。
湿地帯の葦原では、オオヨシキリが甲高く鳴いている。
沼に面した細道に入ると、足裏に柔らかな草が絡みつく。
少し湿った草の冷たさが心地良い。
太陽が雲の切れ目から顔を出し、地面に長い影を落とした。
駅舎に続く短い坂道を上る。
目の前に、木造の小さな駅舎が見えてきた。
兜沼駅だ。
駅前はひっそりしていて、バス停も無人。
駅舎の壁には、古い時刻表が貼られていた。
風でページが少しめくれている。
ベンチに腰掛けて、歩き切った足を休める。
靴を脱ぐと、足先が少し痺れている。
冷たい湿地を踏み越えた感覚が、まだ残っている。
静かな午後、沼のほとりには誰もいない。
鳥の声だけが響く。

兜沼を眺めていると、遠くで水鳥が静かに泳いでいるのが見えた。
湖面は穏やかだ。
宗谷の旅は、どこまでも静かで、空気が澄んでいる。
小さな駅、長い道。
足裏の疲れと、草むらの匂いと、ひんやりした朝の風が、今日の記憶に残った。
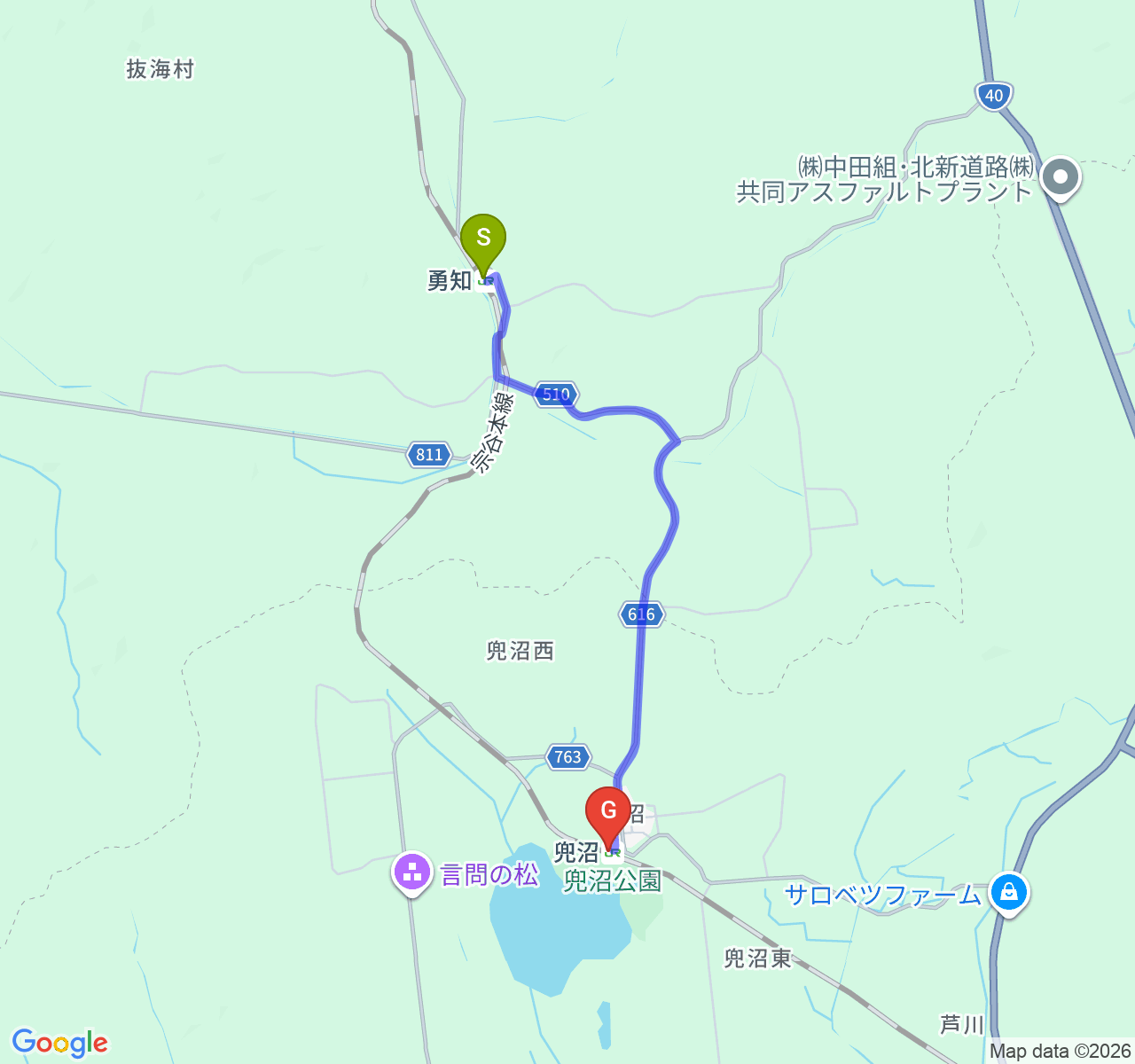
コメントを残す